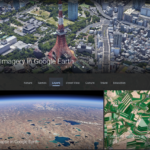浅石卓真です。本連載ではこれまで、学校図書館による探究の支援に向けて、探究の背後にある教育思想や学校図書館に期待される役割について紹介してきました。今回は番外編として、「探究」とは対極にある、教科書を中心とした「習得」型の学びについて考えてみます。日本の学校教育は、(近年、変わりつつあるとは言え)教科書を中心としたものが主流ですが、なぜそうなっているかを理解することは、探究的な学びの位置付けを考える上でも有益だと思います。
日本語の「学び」は、「真似ぶ」に由来すると言われています。江戸時代の庶民は寺子屋で学んでいましたが、そこでの学びは手習いと呼ばれ、師匠が書いた文字の真似をして書く練習が中心でした。それらは商売や日常生活に不可欠な読み書きを教えるためのもので、子どもは寺子屋で基本的な読み書きを覚えてから、稼業に従事したり年季奉公に出たりしました[1]。寺子屋の入門者には人口の多数を占める農民も含まれ、江戸時代末期の日本のリテラシーは世界でも有数の水準であったと言われています。
江戸時代にこのような学びが広まったのは、社会が、文字や数値を記録した文書をやり取りする法治と契約を前提とするようになったからです[2]。農村では、戸籍は村ごとに作成され、領主への出願や旅行や転居にも村の証明が必要でした。年貢徴収や行政を百姓が請け負う村請制という仕組みも、読み書きの普及を促したと考えられます。村々に読み書きのできる人々が一定程度いなければ、年貢徴収や行政を村が請け負うことはできないからです。また都市部でも、町人が商取引のために読み書き算盤を必要とする社会が形成されていきました。
寺子屋では、主に日常生活に関連した教材が利用されました。特に平仮名の『いろは』や『文章』『人名』などは、手習いの手本として多くの寺子屋で利用されていたようです[3]。このうち『文章』は日用的に使われる短文の文章、『人名』は姓の頭字や姓名の単語集です。その他、近郊の町村名を単語集として手習いの手本にした『村名』『町名』のほか『五十三次』『国尽』なども使われました。これらのことから、経済的な交易地や街道に関する地誌的な知識が、生活に欠かせないものであったことが窺えます。
学びが進むと、『商売往来』『消息往来』などのいわゆる往来物が教材となりました。『商売往来』は商売のための帳簿、帳面の種類と名称、商品名など商売を含めた日常生活に必要な単語を、『消息往来』は手紙文に使う単語を手習いの手本にしたものです。往来物という名称は、書状の往来(往信と返信)に由来しており、一定の様式に従って文書を書けるようにするための手本でした[4]。それが江戸時代になると、各地の地理や歴史あるいは商売に関する用語や文例を示したもの一般が、往来物と呼ばれるようになります。日々の生活で必要な文書を作成するための教材と言えます。
一方、社会の指導者層であった武士は、治世のために学問を学び教養を積む必要があると考えられました。そこで、武家の学校である藩校では、江戸時代の指導理念である儒教、特に朱子学が教えられ、教科書として経書、史書、詩文集などが用いられました[5]。ここでの学びの中心は素読、すなわち声に出して読むことでした。素読では、意味を捉えずに声に出して読むことを暗唱するまで繰り返します。素読が一定のレベルに達したら、内容を理解するために講義が行われ、その後は会読(会講)や輪講と呼ばれる学習へと移っていきました。
このように江戸時代の学びは、教材となる書物に記された文字をそのまま筆写したり音読したりすることが中心でした。それが明治時代に入ると、文字の読み書きではなく、知識の教授が重視されるようになります。その背景として、日本が短期間で西欧諸国に追いつく手段として教育が位置付けられたことがあります。このことは、1868年の学制発布直後の教科書が、欧米のものを翻訳・翻案したものが多かったことからも窺えます[6]。当時の日本では国家目標に則した教育内容が定められ、教科書を通じてそれを伝達する仕組みが整えられていきました。授業のあり方も効率が重視され、児童・生徒全員への一斉教授法が採用されました。
もう一つの背景として、学校教育が統合的な日本国民の育成の手段とされたことがあります。すなわち、児童・生徒は天皇に仕える皇国民となることが求められ、教科書を通じて皇国思想が刷り込まれました。例えば、戦前の筆頭教科である修身の教科書には、教科書の内容は熟読暗記させるべきものと書かれています。大正時代には、児童・生徒の個性を重視する教育(大正自由教育)が一部の私立学校で取り組まれることもありましたが、1931年の満州事変後には、軍国主義教育のもとで教育への国家統制はさらに強化されていきました。
そして教科書も、国家目標に即した唯一のものに統制されていきます。学制発布後しばらくは、地方ごとに多様な教科書が使われていました。それが1886年以降は検定制度が実施され、特に小学校では詳しい規定が設けられました。1903年に教科書の国定制度が成立した直接のきっかけは、教科書採択をめぐる大規模な汚職事件でしたが、国民思想の統一のために特に小学校の修身では教科書を国定にすべきという意見は、既に以前から現れていたようです。国定教科書はその後、多くの教科で発行されるようになり、日本の学校における教科書の地位は揺るぎないものになりました。
国定教科書のみを利用した学校教育は、戦後GHQ/SCAPにより一旦否定されますが、1950年代における占領政策の転換をきっかけに、再び教科書を中心とする学習に戻ることになります。当時の日本の経済復興及びその後の高度成長を担う産業人を養成するために、知識を効率的に身につけることが重視されたためです。これは、明治時代に「富国強兵」「殖産興業」というスローガンのもと、必要な知識を効果的に詰め込むために教科書が利用されたのとよく似ています。この傾向が見直されるのは、多様な価値観の中で「ゆとり」を持たせ、児童・生徒の個性を尊重しようとする1980年代以降になります。
引用文献
[1] 梅村佳代「近世における民衆の手習いと読書:子どもの「器量」形成を中心として」若尾政希(編)『書籍文化とその基底』平凡社, 2015. 引用は p. 124。
[2] 根本彰『情報リテラシーのための図書館:日本の教育制度と図書館の改革』みすず書房, 2017. 引用は p. 83。
[3] 梅村 op.cit. 引用は p. 123-145。
[4] 八鍬友広「往来物と書式文例集:「文書社会」のためのツール」『書籍文化とその基底』平凡社, 2015. 引用は p. 163。
[5] 寺崎昌男・仲新・海後宗臣『教科書でみる近現代日本の教育』東京書籍, 1999. 引用は p. 12-13。
[6] 平田宗史『教科書でつづる近代日本教育制度史』北大路書房, 2004. 引用は p. 37。